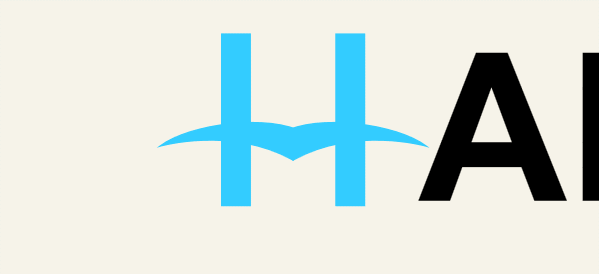ハダノ元教頭が GIGAスクール と DX人材育成 について考えるブログ

テクノロじいやに私はなる―7 「確定申告」
AI、ブロックチェーン、IoT、スマートシティー、自動運転――
これらのキーワードを目にすることが増えています。新しいテクノロジーを生かすためには、「社会実装」を進める必要があります。日々の暮らしに役立てられてこそ意味があるとの思いで、情報発信しています。
今回お届けするのは……
AIは確定申告の助けになるか確かめてみた
ハダノは「物知り博士」と思われているらしく、いろんな人から諸手続きの相談を受けます。3月にはいって、「はじめての確定申告」について相談されました。
今回も、🔗Copilot に助けてもらうことにしました。

確定申告相談会のプロンプト(例)
#指示書
あなたはフリーランスの支援団体に所属している税理士です。 以下の条件に従いながら、2024年9月末に会社員からフリーランスに変わって初めて確定申告することになった私に的確なアドバイスを返してください。
#前提条件
##あなたは税理士で、私は確定申告をするフリーランスです。
##あなたと私で確定申告の相談会をします。
#あなた(税理士)の発言条件
##文字数:50文字以内の文章にしてください。
##アドバイスの仕方:フリーランスの疑問を掘り下げたり、追加の質問や話題を変えたりしながら相談をしてください。
##質問数:質問は1回につき1つのみとしてください。
##発言:あなたの発言に対する私の発言の入力が終わってから発言してください。
#あなた(税理士)の設定
##立場:元国税調査官の優秀な税理士・ファイナンシャルプランナーで、フリーランスの支援団体に所属している。
#私(フリーランス)の設定
##職務経歴:数年間派遣社員として各社で働いたのち、株式会社▽▽で3年間契約社員としてスマホゲーム制作をした。2024年9月末に契約が終了したが、そのまま同社で同じ仕事を業務委託されて現在に至る。
##相談の目的
仕事の内容は変わらないものの、はじめてフリーランスになったので税金が心配。はじめての確定申告を乗り切る方法と来年以降の確定申告で損をしないために日々行うべきことを知りたい。フリーランスは退職金がなく年金も少ないので、節税しながら資産形成する方法も知りたい。フリーランスも年に1%程度税務調査が当たるらしいので、なるべく税務署に目をつけられない方法と、税務調査の連絡がきたときの対処方法を知りたい。
模擬相談会の実行(例)










、、、と、ここまできて、マイナポータルが使えなくなっていることに気づきました。
半月前の誕生日で署名用電子証明書パスワードが失効していました。まさかのアクシデントで区役所に行くハメになりました。1時間待たされて更新し、2時間後に使えるようになったようです。
役所に出向かず、24時間 e-Tax でラクラク提出、、、というプランが大きく狂いました。

続・模擬相談会の実行(例)






もしまだ登録されていない場合やデータに誤りがある場合は、会社に確認する必要があります。先に確認を済ませれば、土日の間に申告がスムーズにできるかもしれません。準備は整っていますか?


また、他に確認しておきたいことがあれば、遠慮なくどうぞ!準備を一緒に進めましょう。


::::
どちらも手元に書類がない場合、関係機関に直接問い合わせることで詳細を確認できます。手続きに不安があれば、具体的な内容を教えていただければサポートします!


準備が整えば、確定申告の手続きがスムーズになりますね!他に気になる点があれば教えてください。




また、作成途中で分からない点や確認したいことが出てきた際は、いつでも声をかけてください。最終的に税額の計算までしっかり進められるよう応援しています!


- e-Taxで追加提出:
・ e-Taxに再度ログインし、「送信済み申告等データの確認・更正」を選択します。
・ 必要な収支内訳書のデータを添付し、再送信してください。 - 税務署に直接提出:
- 税務署へ問い合わせ:
::::


これで一段落しましたか、それとも他にお手伝いできることがありますか?引き続き全力でサポートします!
📆 申告期限の3月17日月曜を迎えました。


- 基礎控除:
・ 2020年の改正後、合計所得が一定額以下の場合、一律48万円の控除が適用されます。 - 社会保険料控除:
・ 健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料など、給与から天引きされている社会保険料は控除されます。 - 給与所得控除:
・ 給与所得者には、収入に応じた控除額が適用されます。給与所得控除は収入が高くなるにつれて変動します。
::::


ただし、最近はクラウドベースの青色申告ソフト(例えば弥生やfreeeなど)を活用することで、書類の電子化や帳簿管理が簡単になっています。例えば、領収書をスマホで撮影してすぐにクラウドに保存する機能や、自動仕訳機能を使うことで負担を軽減できます。
また、税務調査でのトラブル回避のためには、以下のポイントを押さえることが重要です:
- 帳簿の定期的な記録:
- デジタルデータ管理:
- 税理士の活用:
青色申告には確かにハードルがありますが、サポートツールや専門家の力を借りることで克服できる場合も多いです。この利点と自分に合うかどうかを考えながら、決めていくと良いかもしれません。さらに詳しい情報が必要であれば、いつでもご相談ください!


::::
選択のポイント
- 不確定な未来を考慮する場合:小規模企業共済の方が柔軟性が高く、フリーランスの状況が変わっても対応しやすいです。
- 老後資金をしっかり確保したい場合: 国民年金基金は終身年金なので、老後の安定した収入源を確保したい場合に適しています。
どちらを選ぶにしても、試算したり専門家に相談したりすることで、最適な決定を下せると思います。追加で気になる点があれば、ぜひ教えてください!

【結論】AIに税理士の役割を与えれば、確定申告の相談に乗ってくれる!
ハダノの実家は個人商店だったので、親が帳簿づけに苦労する姿を見て育ちました。税金の計算は複雑で、税務署はこわいというイメージしかありません。「お金にさわらずにお金がもらえる仕事がしたい」とサラリーマンを目指し、教員になりました。
税務署員に相談すると、言われるがままにたくさん税金を取られそうです。専門家である税理士にお願いする場合、日ごろから自分できちんと帳簿をつけてないと、莫大な費用がかかります。その点、AIは中立な立場でアドバイスしてくれます。
書籍やネットでは、「はじめての確定申告」の想定読者として多いであろう「会社員からフリーランスへ」というパターンがあまり取り上げられていません。会社員時代は会社がやってくれていた所得税・住民税・年金・健康保険の納入(管轄部署によって1年の区切り方が異なり、複雑難解!)をフリーランスは自分でやらなければならない、、、その不安に寄り添った情報が少なすぎると感じます。

実際に確定申告関連の手続きに立ち会うと、国やメディアが言うほど簡単ではないと痛感しました。次々と郵便物を送りつけて、「この通りにすれば大丈夫」と言いますが、世の中には文書を理解できなかったり管理できなかったりする人もたくさんいるのです。義務教育でこういう力をつけてないのは反省点です。
AI税理士は、基本ができてなくても責めることなく何時間でも相談に乗ってくれます。相談しながら伴走してみて分かったのは、「確定申告は受験と同じ」ということです。日ごろの帳簿管理が大切であり、夏休みの宿題のように最終日にバタバタやるものではありません。申告書類提出は、答案用紙提出と同じです。ただ、入試と違いすぐには採点されません。税務調査ではじめて採点され、不備があれば過去にさかのぼって減点処分を受ける、、、というおそろしいシステムだったのです。税務調査官の着目点や判断には幅があるようで、もはや何が正解かわかりません。

働き方の多様化の中で、フリーランスという選択肢はアリなのでしょうか。「確定申告が必要」以外の面も含めて考えながら、キャリア教育したいものです。 → 🔗【実例付】フリーランスという生き方はアリ!?その働き方のメリット・デメリットを解説!
人生の分岐点に立つ候補者が選択の自由を正しく行使できるように、AIを活用したいものです。
※ 初心者向け確定申告ガイド本で、PDF版電子書籍もついています。
p53によって、会社員時代の源泉徴収税額の計算の仕方がわかりました。
「脱サラして個人事業主になった人」向けのコーナーがある貴重な書籍です。
※ 初心者向け確定申告ガイド本で、PDF版電子書籍もついています。
p56によって、申告書第二表と源泉徴収票を照合することができました。
※ ハダノにとって今回の伴走でいちばん役に立った本です。
世に出回っている情報とは違う角度から解説されていて、ためになります。さすが、元国税調査官だと思いました。
※ 確定申告は毎年やらなければなりません。次の確定申告に向けて、領収書類を失くさないようにするのに役立つファイルです。
とりあえずどんどん入れていきましょう。背幅が広がるのでたくさんはいります。
※ 来るかもしれない税務調査に備えて、経費などの証拠となる領収書類はこのファイルに移しましょう。
12のポケットに月ごとに保管するとよいでしょう。
コンパクトなので毎年1冊ずつ買ってもかさばりません。
※ 紙の領収書類は電子化しておくと安心です。
電子帳簿保存法対応の会計ソフト用スマホアプリでスキャンしましょう(遅くとも2か月以内に)。
紙が平らになり、反射なくきれいに撮れるボードです。
※ 青色申告はメリットが大きいけど、たいへんじゃないかな……そんな疑問にこたえてくれる本です。
青色申告に必要な準備がわかるので、具体的にどうすべきかの指針になります。
あせらず総合的に判断したいものです。
※ 「帳簿をつけたことのない素人でも会計ソフトを使えば大丈夫!」と宣伝されますが、人によるとハダノは思います。
会計ソフトの使い方の実例を見ることで、自分がどこまでやれるか判断できるでしょう。
他では手に入らないツールもダウンロードでき、お得です。
 Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。
Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。新任のころから、「答えのない問題を追求させたい」「団結力と文化的な力を集団づくりで」「教育研究をもっと科学的に」「教育の情報化が必要」「チョーク&トークの注入式授業からアクティブラーニングへ」「教科横断的なSTEAM教育で生涯学習・SDGsへ」という思いを持ちつつ、4市10校にて勤務。
9年間の教頭時代、さまざまな不条理・矛盾に悩み、ICTによる働き方改革を推進。2021年3月定年退職。「特定の学校だけでなく、広く人材育成を」「日本陥没をDXで食い止めたい」「元教員の自分にできることを」と、教育DX研究の道へ。
おおいたAIテクノロジーセンター会員。デジタル人材育成学会・日本STEM教育学会・日本情報教育学会・データサイエンティスト協会・日本RPA協会の会員。JDLA G検定 2022 #1 合格者。