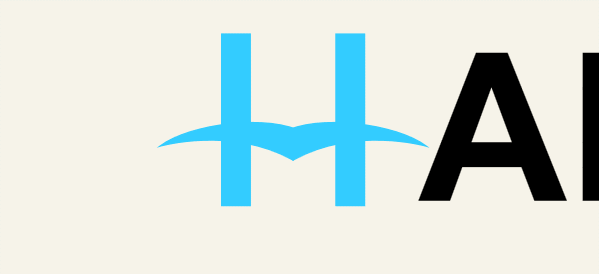ハダノ元教頭が GIGAスクール と DX人材育成 について考えるブログ

分断でてーへんだー
20世紀少年は、明るい21世紀を夢見ていました。科学文明が発達し、「いつでもどこのだれとでも自由に話せるようになる」「相互理解が進み平和で豊かな世界になる」と……
実際はどうなったでしょうか。テクノロジーによって夢に近づいた部分もあれば、かえって後退した部分もあります。特に危機が叫ばれるのが「SNSによる分断」です。
科学の子の夢をかなえるにはどうしたらよいのでしょうか。
今回お届けするのは……
情報人権教育で異質対等な共創社会を!

SNSによる分断
- トランプ大統領再選
- 兵庫県知事再選
- 各地の紛争
- 災害予知
- コメ騒動
- 少子化問題
など、SNSが極端な意見の応酬を煽り、人々が分断されていく姿が見られるようになりました。
無料で誰とでも情報のやり取りができる便利さの裏には、アテンションエコノミーが潜んでいます。人々の「関心」が売買されているのです。
視聴率が民放TV局の収益に直結しているのと同じように、SNSで注目される情報は、直接・間接に利益を生みます。「インフルエンサーおすすめの商品がよく売れる」「閲覧数や高評価数に応じて報酬が支払われる」ほか様々な収益化の網が張り巡らされているのです。パッと目をひく刺激的なものばかりバズって、じっくり考える機会にはなりそうにありません。 → 🔗嘘の拡散スピードは、事実よりも〇倍速いことをご存じですか?
異なる立場同士のコミュニケーションを円滑にし、分断を乗り越えるにはどうすればよいのでしょうか?
認知バイアスの功罪
人類学者や認知科学者によれば、ホモサピエンスの繁栄にはヒト特有の認知バイアスが深く関わっているようです。
によれば、乳幼児も「対称性バイアス」によってことばをものすごいスピードでおぼえます。思い込みの原因である「確証バイアス」などで「うわさ話と作り話」が盛んになり、大集団化が可能となりました。
認知バイアスは、誤判断しがちという欠点がありながら、限られた認知能力で世界を捉え、学び、渡り歩いていくために不可欠なものでもあります。進化の過程でホモサピエンスに備わったこの「認知バイアス」をなくすのではなく、理解して対応したいものです。 → 🔗「言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか」
にあるように、SNSは認知バイアスを増幅させる可能性があります。特に、確証バイアスやエコーチェンバー現象は、SNS利用者の情報収集や意見形成に影響を与え、偏った考え方を助長する可能性があります。 → 🔗「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?

は、まさにバンドワゴン効果(「みんながやっているから自分も」と、流行や多数派に影響される傾向)でしょう。認知バイアスによるファスト思考には、スロー思考によるチェックを加えたいものです。
- 初期の国産アンドロイド機には品質の低いものがあり、アンドロイド全体のイメージを落とした
- Appleからの厳しい販売ノルマのせいで、iPhone が優先的に売られるようになった
- 発信力旺盛な若年層によって、iPhone一択という空気が作られた
- 操作性や周辺機器など独特のApple世界がユーザーを囲い込み、乗り換えを難しくしている
ハダノは、ずっと韓国サムスンのGalaxyを使っていますが、高品質でコスパもよく満足しています。特に、Windowsとの相性の良さは、Apple製品とは雲泥の差です。
スロー思考では、客観的データに基づいて考えるのが大切です。iPhoneのシェアは、「世界27%:日本69%」と2.5倍ですが、ここまで日本で流行した原因として、2番の「Appleからの厳しい販売ノルマ」を忘れてはなりません。
、、、つまり、後発のソフトバンクが2008年から「iPhone独占販売」を武器に捨て身のセールスで躍進し、au(2011年~)とドコモ(2013年~)が追随せざるを得なくなったのです。「iPhoneを売らせてもらいたかったら従いなさい」と不平等条約のようなノルマを課され続けているため、Android機の販売は二の次になってしまうのです。
このようなカラクリを知らないと、「日本人は高級志向だからApple製品を選ぶ」と結論付けてしまいます。これは、Macのシェアが「世界16%:日本18%」に過ぎないことと明らかに矛盾します。同調圧力の強い日本ならではの現象に気をつけたいものです。 → 🔗「生贄探し 暴走する脳」
日本のSDGsの課題は、人権・教育
によると、日本のSDGsは人権・教育に課題があるようです。
ジェンダーギャップ2025では、148か国中118位となっています。女性を差別する古い価値観が残っている国なのです(5番のジェンダー平等に課題)。

ハダノは市の人権教育推進教員として活動した経験があります。ケガレを処理することが多い部落の人々が差別されてきた歴史を学びました。ケガレのうち特に差別と深く結びついていたのが「死、出産、血」の三不浄です。このうち2つは女性特有のケガレであり、日本の伝統的価値観の中に女性差別が深く根付いているのです。
「少子化は、女性の社会進出が引き起こした」説もジェンダーバイアスによる決めつけです。
家父長制が強く女性が活躍しにくい地方から都会へと若い女性が流出し、地方は嫁不足に陥りました。では、東京はどうでしょうか。
によれば、結婚に前向きな若者は全体の 86.1% にのぼり、全体の 76.4% が「理想的な子どもの数」は2人以上と回答しています。決して希望しなくなったのではなく、希望が実現しにくくなっているのです。経済的負担増の不安に加えて、女性は家事育児の負担増とキャリアロスの不安にさいなまれます。

女性の不安は、結婚相手に求める年収を吊り上げます。SNSやマッチングアプリが男性のスペック相場の上昇に拍車をかけ、女性の上方婚(高望み)傾向が非常に強くなります。そうすると中間層の男性が婚活市場で見向きもされなくなって、全体の成婚率が低くなるはずです。
マッチングアプリは出会いのチャンスを拡大したように見えて、「一握りのプレイボーイがガールハントし放題でさらにもてるようになる狩場」を提供したに過ぎません。 → 🔗【婚活の落とし穴】出会いが多すぎて選べないあなたへ。「結局、容姿で選んでしまう」その裏にある、本当の気持ち
結婚した女性が産む子どもの数があまり変わってないことから、少子化の実体は「不本意未婚化に伴う少母化」だと言えます。
、、、こんな「子持ち様」と「おひとり様」の分断を招いたのもSNSです。かつては「お互い様」だったのに、今やぜいたく品となってしまいました。
そもそもホモサピエンスは、未完成で生まれ何人もの手で何年も育てられてきたからこそ高度な社会を築けたのです。子育てが迷惑がられる社会は滅びます。落ち着いて考えればわかるはずです。 → 🔗「男女差別がなくなると、少子化も改善するよ」というデータを示すと、なぜ反論(クソリプ含む)が押し寄せるのか?

を見ると、ジェンダーバイアスの根深さがわかります。
「デートでおごる」問題も、「男がおごる or 割り勘」であって、「男がおごる or 女がおごる」ではないのは、ジェンダーバイアスです。ユニセックスの衣類にズボンはあるがスカートがないのも、ジェンダーバイアスでしょう。
選択的夫婦別姓議論が進まないのは、家父長制と結びついた戸籍制度が残っていることが大きいと考えられます。姓を変えたくないのは、生まれた「家」の姓にとらわれているからです(ハダノは通算4つ目の姓)。マイナンバーで住民登録をし全ての手続きを行うしくみになれば、姓はなくても支障ないはずです。
ジェンダーバイアス解消の道のりはまだまだ遠いようです。人権教育の充実が求められます。
認知バイアスによって悪化する社会的ジレンマ
「解決できる問題はすでに解決している」現代、どうしても解決できないのが「社会的ジレンマ」です。個人が自身の利益を追求する行動が、社会全体にとって望ましくない結果をもたらす状況のことで、環境汚染や交通渋滞などが挙げられます。

は、2024年8月の記事ですが、状況の正確な全体像がわからないまま個人が良かれと思って行動すると日本全体が混乱するわけです。1年間たとうとしていますが、「令和の米騒動」は収まりそうにありません。SNSではうわさ話と作り話が飛び交い、事態を悪化させています。
単純化バイアスによる善悪二元論は困りものです。「JA全農黒幕説」はかなり拡散されたようですが、そんな単純な話のはずがありません。🔗ピーター・センゲ著「学習する組織 ― システム思考で未来を創造する」 に登場するビールゲーム(ビールの製造から供給までの役割を分担し、発注と納品を繰り返すロールプレイングゲーム)では、しばしば需給バランスが崩れて過剰在庫や欠品が発生してしまいます。
- 部分最適は全体最適につながらない。
- コミュニケーション不足や情報共有の遅れが、システム全体の混乱を招く。
- 過去の意思決定が、現在の状況に影響を与える。
- システム思考とチーム学習の重要性。
、、、などの教訓が得られます。
特に2番の情報共有の遅れは致命的です。タイムラグを頭に入れずに目先の対応をしていると、収拾がつかなくなります。米の場合、生産段階で最低1~2年のタイムラグが出るので、流通の各段階でベストをつくしたとしてもなかなか正常化できないでしょう。4番のスロー思考による複雑性の理解が重要です。安易に陰謀論に飛びついてはいけません。
「米価を2倍にした犯人はJA全農だ!」という声が強まる中、ハダノは不思議なことに気づきました。NHKのスポーツニュースで、世界卓球2025ドーハの話題がまったく出なかったのです。
中国をはじめ世界のトップ選手がみんな出ている大会で、日本は「金1 銀1 銅2」と大健闘したのに、結果すら放送されずに終わりました。競技人口が十数分の1のボルダリングの試合シーンは出ていたので、時間枠の問題とは思えません。「大谷の打席シーンはヒットじゃなくても放送するのに変だな(種目差別では?)」と感じました。

以前のNHKはもっと卓球の結果を放送していました。メインスポンサーである「全農」の文字がはいったユニフォームがTVに映ると、時節柄まずい……そんな忖度から放送を控えたのでないことを祈ります。 → 🔗【卓球】64年ぶりの男子ダブルス優勝!日本勢が熱戦を制した世界卓球ドーハ大会を振り返る
分断を乗り越えるには
ホモサピエンスは、身体能力で劣る分を「仲間の力」でカバーし、より大きな集団をつくることで生き残ってきました。熱帯に住んでいたころは、食べ物は腐る前に分かち合っていたはずです。そうして、与える喜びを感じるように進化しました。
高緯度地方へ進出すると、冬に備えて食糧を蓄えるようになり、富の集中が起きてきたと思われます。集団が大きくなるほど、権力層を頂点とする階層構造が生まれやすくなります。他の集団と争う中で、階層構造はより強固になっていきます。
「みんな仲間になってしまえば争いはなくなるはず」なのに、分断によるいがみあいがたえません。階層メンバーが固定していない場合、自由競争と言う名の敵対的競争が生まれます。権力層が強権を発動するか、外敵を作ることで結束をはかるしかありません。
たとえ、権力層を民主的に選出しても、しだいに富と癒着して腐敗してゆくものです。運営側(胴元)にすり寄らなければ勝てない「無理ゲー」だらけになってしまいます。「みんなが望んだ麻薬のような秘密道具」であるSNSの運営企業による「プラットフォーマー帝国主義」が世界をおおいつつあります。これらは典型的な社会的ジレンマです。

少子化問題・教育問題・環境問題は、短期間で成果が出ません。3~4年に一度の選挙で公約達成度を評価できないテーマは軽視されます。ファスト思考に偏るわけです。この問題を解きほぐすのは簡単ではありません。
- 「善悪二元論」にとらわれず、🔗「どっちもどっち論」 も取り入れる
- Win-Winになるために、他人と比較するより過去の自分と比較する
- 自慢合戦・マウント合戦に乗らないようにし、SNS依存を回避する
- 封建的な序列化慣習(先輩・後輩・同期)を改める
- 〇〇主義にとらわれず、多様な意見を組み合わせ、よりましな選択をする
- システム思考を学び、複雑性の理解に努める
- 認知バイアスを知り、内なる差別意識に気づく
- 誤情報に気をつける → 🔗みんなでファクトチェック……
- 「心のAI」による長期シミュレーションでエビデンスのある政策を立案する → 🔗「人間の心」を間違いも含め再現できるAIが開発される
教育分野でこれから力を入れたいのが、「情報人権教育」です。
情報リテラシーと人権教育は、現代社会において不可欠な要素です。情報リテラシーは、情報を見極め、適切に活用・発信する能力であり、人権教育は、自己と他者の人権を尊重し、差別や偏見をなくすための教育です。互いに補完し合う関係のこれら二つを組み合わせることで、情報社会における人権侵害を防ぎ、より良い社会を築くことができます。

認知科学をベースにした情報人権教育で、DEI(多様性・公平性・包括性)を進化させ、異質対等な共創社会を築いていきたいものです。
【まとめ】情報人権教育で分断を乗り越え、異質対等な共創社会を!
- 人は認知バイアスによるファスト思考だけで思考停止しがち
- SNSが認知バイアスを増幅し、分断を生んでいる
- 敵対的競争が激化し、社会的ジレンマが深刻化
- スロー思考で俯瞰的多元的に複雑性の理解をし、長期的視点で解決策を検証し続ける必要がある
- 情報人権教育で異質対等な共創社会をつくっていきたい
※ スキーマ(思い込みの塊)に頼り、論理の跳躍を伴う推論をしがちなのが人間。
コミュニケーションの達人になるには、形だけまねるのではなく、失敗を分析・修正して成長の糧にすることから。
ヒトの非論理性を自覚しながら論理を組み立てていく科学者たちには感謝しかありません。
※ 「日本には世間体という戒律がある」「出る杭を許さず足を引っ張る」「協調性という蟻地獄」など同調圧力の強い日本をイタリアと比較しながら論じていて、興味深い本です。
養子に出された子は愛着障害……のくだりにハダノはドキッとしました。
※ これまでは、経営者だけが戦略を練るために学び、従業員に指示を出す「管理型組織」が多くの企業で慣行されてきました。
変化の激しい時代に対応するためには、従業員自らが考えて、組織の成長や個人の成長のために「自主的に学ぶ」風土を持った組織づくりが不可欠とセンゲは説いています。
国もそうありたいとハダノは思います。
※ 善悪二元論に流されていた自分を「どっちもどっち論」で見つめ直すことができます。
「学校に適応できない子ども」→「子どもに適応できない学校」という視点の切替、軍国主義の名残である体育会系の「先輩・後輩・同期」など多くの気づきが得られます。
 Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。
Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。新任のころから、「答えのない問題を追求させたい」「団結力と文化的な力を集団づくりで」「教育研究をもっと科学的に」「教育の情報化が必要」「チョーク&トークの注入式授業からアクティブラーニングへ」「教科横断的なSTEAM教育で生涯学習・SDGsへ」という思いを持ちつつ、4市10校にて勤務。
9年間の教頭時代、さまざまな不条理・矛盾に悩み、ICTによる働き方改革を推進。2021年3月定年退職。「特定の学校だけでなく、広く人材育成を」「日本陥没をDXで食い止めたい」「元教員の自分にできることを」と、教育DX研究の道へ。
おおいたAIテクノロジーセンター会員。デジタル人材育成学会・日本STEM教育学会・日本情報教育学会・データサイエンティスト協会・日本RPA協会の会員。JDLA G検定 2022 #1 合格者。