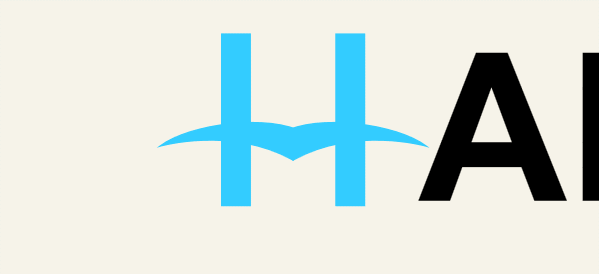ハダノ元教頭が GIGAスクール と DX人材育成 について考えるブログ

日本のポップカルチャー、推しまーす!
ゲーム音楽演奏キャンペーンに参加してみた
ALTはアニゲー好きが多い?
教員にとって最も身近な外国人はALT(外国語指導助手)です。彼らに日本に来た理由を尋ねると、「日本の文化に興味があったから」と答えます。
🔗外国人は日本のなにに興味を持つの?1位はだんとつで「ゲーム・アニメ・マンガ」 ……からもわかるように、伝統文化よりもアニメ・マンガ・ゲームに興味が集中しています。
政府は「クールジャパン」を推進して、①アニメーション分野、②ファッション・デザイン分野、③美容分野、④食分野 を学びにきた外国人に在留資格を与えたいようです。🔗ポップカルチャーで日本の魅力を発信! によれば、やはりポップカルチャーが柱になりそうです。
ただ、日本の仕事に魅力を感じる外国人が少ないのが課題です。給料が少なかったり、仕事がきつかったりすれば、そっぽを向かれるでしょう。少子高齢化による労働力不足を外国人で補うためには、DX推進が必須です。

ゲーム音楽は、日本の文化
ハダノは、ゲームをプレイする習慣がありません。プログラミングの題材としてゲームに関わることはありますが、動作が確認できたら終わりです。
ゲームの魅力は理解しているし、ゲーミフィケーションは教育の手法として有望だと考えています。日本のゲームは世界中で愛され、ゲーム音楽はアニソンとともに重要なジャンルになっています。
あるとき、「新作ゲームの音楽を演奏して動画を送ろう」というキャンペーンを知りました。 → 🔗「集え!ポケモン吹奏楽部」~ポケモンSVと吹奏楽のコラボ!?
「集え!ポケモン吹奏楽部」は、2022年11月11日~2023年1月16日まで、ポケモンSVの「メインテーマ」の演奏動画を募集していたキャンペーンです。
募集要項としては、
- 部活, チームで応募
- 個人で応募 (金管部門, 木管部門, 打楽器・その他部門)
に分かれています。

部活全体で演奏して応募するのも魅力的ですが、個人でも自由に練習して応募できる(曲の一部でもよい)というのは粋な取り計らいです。
木管部門に挑戦!
吹奏楽の楽器を持たないハダノは、ウインドシンセで木管部門に挑戦してみました。
練習期間が短くてあせりましたが、DAWでMIDI入力し、オーボエの音色を当てて雑音なしで録音することにしました。DAWを使った練習では、「テンポを落とす・メトロノームを鳴らす・お手本の音に合わせる」など自在にできるので助かりました。目標にしていた前半部分(転調前)が吹き込めたので、動画を送信しました。
吹奏楽経験のないハダノは、ウインドシンセでMIDI入力しました。
— ハダノ元教頭|教育DXブログ (@kyodx_com) March 19, 2023
「吹奏楽の楽器じゃないと参加賞もらえないかな」と心配でしたが、特製クリアファイルが届きました。
キャンペーン事務局の度量の大きさに感謝です。#教育DX pic.twitter.com/ChYU0WKsUv
「吹奏楽の楽器じゃないと認められないかな」と心配しながら参加賞の到着を待ちました。特製クリアファイルが郵便で届いたときは、「やってよかった!」と思いました。みんなの演奏をつなぎ合わせた動画には、ピアノ・ヴァイオリン・リコーダー・鍵盤ハーモニカ・エアロフォンで演奏している姿も見られました。キャンペーン事務局の度量の大きさに感謝です。
日本のポップカルチャー業界は大丈夫なのか
🔗「ブラッククローバー」に「異世界おじさん」…アニメの放送休止・延期がなぜ続く? 「日本のアニメ業界がいまだに手描きの原画に頼ることが…」
……を読んで、不安が的中しました。「テレビの高解像度化に伴い、アニメーターの給料が下がる」とかなり前から言われていました。1枚描く労力が4倍になるのに単価が同じままなら時給が4分の1になるのは当然です。
原画の間をつなぐ動画や仕上げの行程のほとんどを中国などに頼っている状態は、食料自給率が低いのと同じくらい危機的です。ここはぜひ、DXで解決したいところです。まずは、手描きを減らして制作工程のデジタル化を進めていくべきでしょう。

🔗Blenderを活用して少人数でのアニメづくりを実現! 「モータークイーン」アニメPV ……のように、一般の個人が使うデジタルツールでアニメづくりの大部分(セル部分の動画仕上げ作業以外)をほぼ一人で行える時代になりました。AIを用いた中割などの自動化も取り入れれば、アニメ業界の労働環境は改善できるのではないかと思います。
クリエイターに必要なこと
アニメ業界に比べゲーム業界の場合、CGキャラクターをプログラムで動かす関係で、早くからデジタル化が進んでいました。🔗CGWORLD2023年4月号「とことん深掘り! ゲームのアニメーション」では、ウマ娘・ポケモン・モンハン等がとりあげられています。
クリーチャーズによると、ポケモンS・Vでは、地形変化の大きいオープンワールドに生息するポケモンを表現する必要があったので、モーション数が増えてたいへんだったようです。各工程間のコミュニケーションのため、専用のWikiや短時間のビデオ会議も活用されています。人間・動物・機械類など様々なものを観察し動きを作ってみることを通して、重心移動などの基礎も培われるといいます。
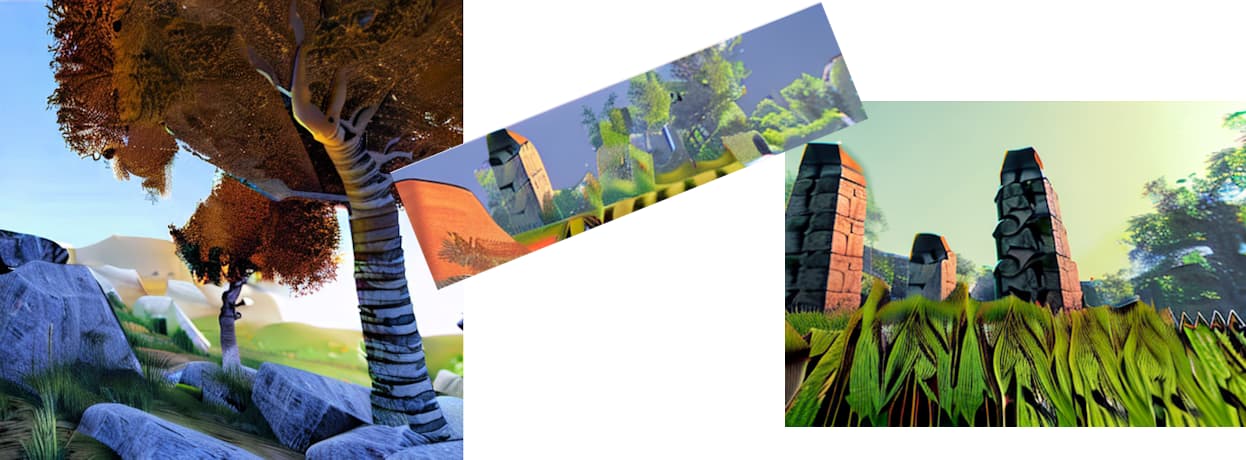
この業界を志す人に対しては、「エンターテイメント以外の分野も含めて、様々なものに興味をもっていた方が良いと思います」とアドバイスしていました。
同じことは、押井守氏も言っています。→ 🔗 押井守が今の若い監督に望むことは? アニメーション業界における批評の不在を語る
彼は、若い監督が全然本を読んでいないことが不満で、「本を読んでいなければ、人と喧嘩もできないよ」「論理的に物を考えて喋る能力がなかったら、喧嘩なんかできるわけないじゃん」と言いたいようです。🔗国民文化祭優勝のごほうびで招待された記念公演 でも、押井氏は「いろんなものを吸収し内面を豊かにしてはじめてクリエイターは作品を創れる」と述べていたことを思い出します。
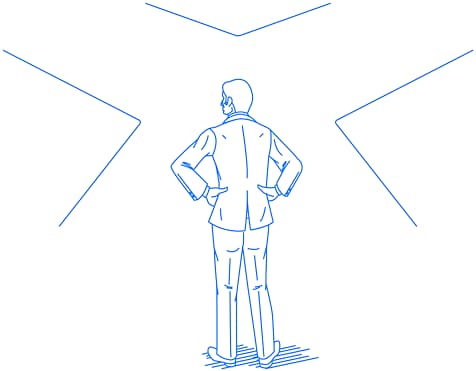
これらは、🔗キャリア教育 としても大切なことです。「ユーチューバーになりたい」「ポップカルチャー業界に入りたい」生徒が「学校の勉強なんかいらなくね?」と疑問をもったとき、きちんと答えられる大人でありたいものです。
ポップカルチャーを教育に取り入れよう
「推し活」が社会現象となって注目されるようになりました。→ 🔗「推し活」の経済効果、企業を動かす
しかし、「クールジャパン」が単なる消費拡大にとどまれば、ポップカルチャーはいずれ衰退するかもしれません。🔗「推し」を社会現象にしたのは、テクノロジーの進歩と同調圧力 ……によると、内輪で楽しむオタクや萌えから、「推し」への変遷を後押したのは、テクノロジーの進歩ということです。技術的変化がユーザーの「参加」を可能にし、女性や子どもも多く加わるようになったのです。ただ受け身で楽しむのではなく、画像・音楽・動画・考察等を投稿し、アクティブに参加・交流するようになったのです。

考察・聖地巡礼という「探究」、画像・音楽・動画・ストーリーの二次創作という「創造」……これはまさに、🔗STEAM教育(教科横断的な探究・創造型教育)でやっていることと同じです。
「地域の文化」を総合学習のテーマにした場合、伝統文化とポップカルチャーを🔗比較文化学 的アプローチで「探究」し、伝統文化をポップカルチャー風に翻案・アレンジする「創造」に取り組むのはいかがでしょうか。
- 神楽のストーリーを漫画・アニメ・特撮ヒーロー物風に翻案し、解説資料(プレゼン、寸劇)を作る。
- 神楽の舞や囃子を取り入れてアレンジし、エモいダンス動画を作る。
- 神楽の衣装・小物・楽器をRPG風にアレンジし、身近な素材で作ったり3Dプリントしたりする。
- 祭りの料理からヒントをつかみ、SNS映えする創作スイーツを作る。
- 祭りの主役のひょうたんを栽培し、ゆるキャラのフィギュアを作る。
- 忠魂碑や戦争遺構にこめられた人々の思いをくみ取り、戦闘アニメ風の物語を作って声優風に朗読する。
- 地域の伝承をベースに、名所を巡るアドベンチャーゲームをプログラミングする。→ 🔗プログラミングシステム「ソックサーガ」
……こんな具合に、いくらでも考えられます。子どもたちにとっては、伝統文化の方が異文化かもしれません。ポップカルチャーとからませることで、主体的に深く「探究」できるに違いありません。

現代日本は、知識偏重の傾向があります。「主要5教科」という呼び方にも表れています。「技能教科」は、頭を使わず言われた通りに「ものつくり」するだけと軽視しがちです。ものつくりは「探究」があって「創造」になるし、調べ学習は「創造」があって「探究」になると思います。探究と創造が教科によって分かれているのなら、教科横断的に両方やればいい……ということでSTEAM教育の出番となるのです。
伝統文化×ポップカルチャーのSTEAM教育は、温故知新になるし、新たなポップカルチャーの担い手を育てることにもつながると期待されます。「クールジャパン」が本物になるのです。
【まとめ】ゲーム音楽演奏キャンペーンに参加して、「推し活パワー」を実感!
最初は、「へー、楽譜が公開されたんだ。クラシック以外の音楽もやってみるか」という軽い気持ちでとりかかりました。やっているうちに、このゲームのことをもっと知りたくなり、ヘビーユーザーに聞いてみました。

オープンワールドになって、良かった点・いまいちな点は?。


自由といいつつ実質的な推奨道順はあって、そこから反れると違和感を覚えるようになっているため....

イベント駆動プログラミングや深層学習AIにその方向性が見えるけど、社会そのものもデータ駆動型に変革したい。

リアル人生ゲームにわくわくを!
キャンペーンの趣旨から、「楽しそうに演奏すること」が大切と考え、キャラクターグッズを集めてデコレートすることにしました。おもちゃ売り場は、子どもたちが大きくなってからご無沙汰でしたが、時間を忘れて楽しめました。はまる人たちの気持ちがわかります。

ゲームの世界観に触れながら「解釈」や「工夫」を加えて作った演奏動画は、ある意味「二次創作」と言えるでしょう。今回の「参加」で、推しキャラへの思い、他の参加者との連帯感、達成感が熱く込み上げてきました。オープンワールドの住人に生命を吹き込むクリエイターたちの奮闘もドラマでした。そんなワクワクを知ろうともせず「くだらんものにうつつをぬかしてないで、勉強しろ」と言い放つ大人は、壁を作っているんだと気づきました。
「推し活」は、壁を壊す巨人のパワーを持っています。「オタクが日本を救う」は未達成ですが、「推し活パワーが社会を変える」は実現しつつあります。それは、テクノロジーに支えられています。ポップカルチャー業界のDXと教育DXが進めば、クールでウェルビーイングなジャパンも夢ではないでしょう。
※ ハダノの近所でもカプセルトイの売り場が増えてきました。
カプセルトイは何が出るかわからないドキドキがありますが、ある程度の大きさのものを確実にゲットするには、こういうフィギュアがいいですね。
※ 月刊のCG・映像クリエイター総合誌です。
アニメ・特撮・SF映画等の制作舞台裏に関する詳細解説が魅力で、ハダノは時々購読しています。
2023年4月号は日本のゲーム業界にスポットを当て、ポケモンSVなどのキャラクターに生命を吹き込むアニメーターの仕事を深掘りしています。
 Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。
Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。新任のころから、「答えのない問題を追求させたい」「団結力と文化的な力を集団づくりで」「教育研究をもっと科学的に」「教育の情報化が必要」「チョーク&トークの注入式授業からアクティブラーニングへ」「教科横断的なSTEAM教育で生涯学習・SDGsへ」という思いを持ちつつ、4市10校にて勤務。
9年間の教頭時代、さまざまな不条理・矛盾に悩み、ICTによる働き方改革を推進。2021年3月定年退職。「特定の学校だけでなく、広く人材育成を」「日本陥没をDXで食い止めたい」「元教員の自分にできることを」と、教育DX研究の道へ。
おおいたAIテクノロジーセンター会員。デジタル人材育成学会・日本STEM教育学会・日本情報教育学会・データサイエンティスト協会・日本RPA協会の会員。JDLA G検定 2022 #1 合格者。